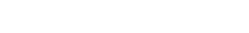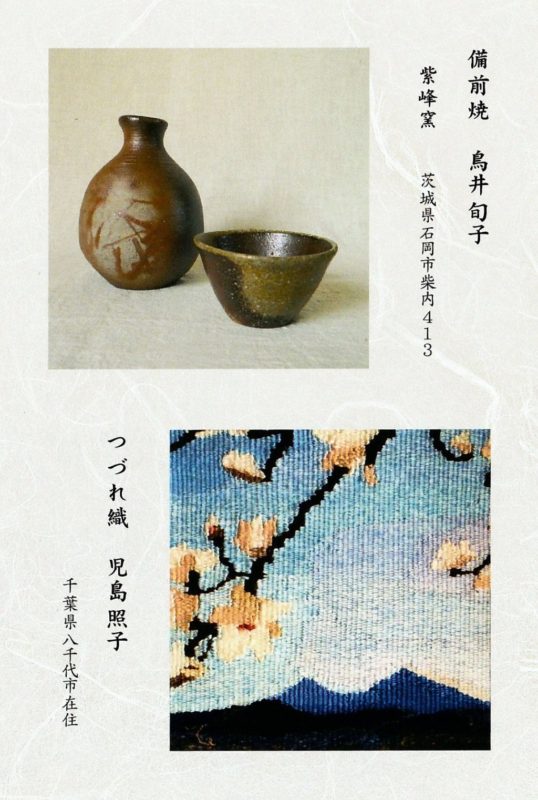シンプルで軽い利休バッグ2020・八寸/九寸|魔除け厄除けの縁起物の総鱗文様の準礼装にお勧めな和装バッグ。
本日は縁起の良い鱗文様の正絹袋帯地からお仕立てをしました利休バッグ(和装バッグ)をご紹介させていただきます。(2020.02.掲載商品)
「黒留袖、結婚式におすすめ、正絹佐賀錦草履バッグセット2017(鱗段/七寸)」2017/01掲載商品
鱗(うろこ)文様は呉服の世界でもよく用いられる縁起物の文様ですが、和装小物の世界でもよく用いられます。弊社でも半衿や帯締め、帯揚げ、扇子、長襦袢の地紋、そして鱗柄の七宝の懐中時計なども人気の高い商品です。
「七宝懐中時計(片面タイプ/鱗柄ほか3種)」2013/10掲載商品(在庫状況はお問い合わせください。)
この鱗、“さかなへん”が付いているので、魚の鱗という意味ももちろんあるのですが、こと文様に関しては龍や蛇などの鱗を指しています。古い鱗を落とす(脱皮する)と同時に、身に付いた厄も一緒に払い落とし、そしてまた再生することから、厄除けや魔除け、そして再生の意味が込められています。
もちろん、硬い鱗により外敵から身を守るという意味もあり、戦国時代の武将の衣服や武具などの装飾にもこの鱗文を見ることができます。
少し余談になりますが、和傘の“蛇の目”にも同じように、魔除けの意味が込められています。本来は“中入り(なかいり)”という傘の中間やや上方にやや太い白い“輪”の入ったものを蛇の目傘と呼んでいました。ちょうど傘を広げてみると、中入りが“蛇(へび)の目”のように見えます。
しかし近年では、無地でも柄物でも和傘全般を総称して“蛇の目”傘と呼んだりしています。ただし、“蛇の目傘”と“番傘(ばんがさ)”はまたちょっと異なりますのでご注意ください。
「蛇の目傘2019|蛇の目《中入り》3種|希少な高級化粧和傘。」2019/04掲載商品
(※店頭販売のみ。在庫内容はお問い合わせください。)
(※ほかにも蛇の目傘の内側に多色の飾り糸を施したものや無地も御座いますが、入荷状況は大変不安定となっております。いずれもWEB未掲載。)
「梅雨入り前だと言うのに今日も雨・・・蛇の目(傘)。蛇の目と番傘の違い。」2010/05掲載(外部サイト・アメブロへ)
さて、余談が過ぎましたが、それでは縁起物の総鱗柄の利休バッグ(八寸、九寸)をどうぞご覧ください。